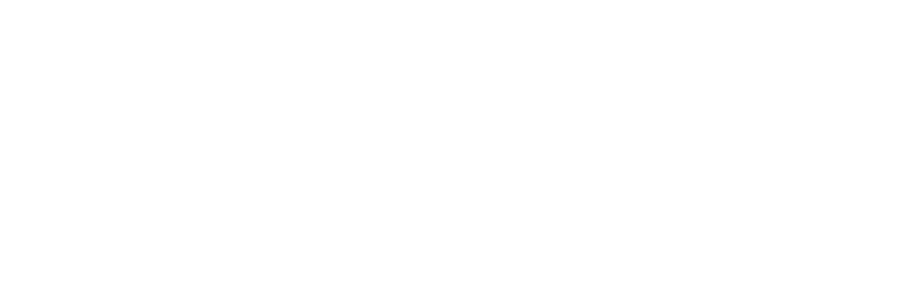自分に万が一のことがあった際、遺言書を遺しておけば遺産相続がスムーズになります。
しかし、いざ作成を検討したときに不安になるのが「遺言書の効力って、どこまで認められるのだろう?」ということではないでしょうか。
また、せっかく作成しても、無効となってしまう遺言書があるのも事実です。
効力を発揮する遺言書と無効になってしまう遺言書には、どのような違いがあるかについても気になるところ。
そこで本記事では、遺言書の主な効力や無効となってしまうケース、遺言書の有効期限について詳しく解説していきます。
これから遺言書の作成を検討している方の参考になると幸いです。
遺言書の効力が及ぶのはどんなこと?
遺言書の効力は、どのようなことに及ぶのでしょうか。
主な効力には下記の8つがありますが、中には相続人の意思によって、内容を覆せるものもあるため注意しなければなりません。
| 遺言書の効力が及ぶ内容 | 記載されている法令 |
|---|---|
| 相続分の指定 | 民法902条 |
| 遺産分割方法の指定 | 民法908条 |
| 遺贈 | 民法964条 |
| 非嫡出子の認知 | 民法781条 |
| 未成年後見人の指定 | 民法839条 |
| 相続人の廃除 | 民法893条 |
| 生命保険金受取人の変更 | 保険法44条 |
| 遺言執行者の指定 | 民法1006条 |
上記の中で「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「遺贈」に関しては、遺言書があっても絶対とはならず、相続人の意向によって覆すことができるケースもあります。
相続分の指定
相続分の指定とは、相続人が複数人いる場合に、特定の相続人に対して「法定相続分とは異なる割合」で財産を指定することです。
例えば「長男に家業を継がせるため、すべての財産を相続させる」「長女が同居してくれていたので、自宅は長女に相続させる」などといった指定を行うことができます。
しかし、相続分の指定は、相続人の意向によって覆される可能性も。これは、民法で定められた「遺留分」のルールによるものです。相続人は最低限の割合で、遺産を相続できる権利を持っています。
遺言書を作成する際には、遺留分に十分配慮することが大切です。
遺産分割方法の指定
遺言書によって、遺産分割方法の指定を行うことも可能です。
例えば「長男には預貯金、次男には自宅(不動産)を相続させる」などを指定しておくことができます。
しかし、相続人のすべての合意がなければ、遺産分割協議書を作成することはできません。相続人全員が、遺言書とは異なる分割方法を望む可能性もあるのです。
したがって、遺言書による遺産分割方法の指定は、相続人の意向によって変更となる場合もあるでしょう。
遺産分割協議についての詳細は、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
遺贈
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に譲り渡すことです。
例えば「お世話になった人に財産を渡したい」「特定の団体に、すべての遺産を寄付したい」というケースで用いられます。
しかし、遺贈に関しても、遺言書の効力は絶対ではありません。相続分の指定と同様、相続人には「遺留分」があるため、それを侵害することはできないのです。
非嫡出子の認知
非嫡出子(ひちゃくしゅっし)の認知とは、婚姻関係がない男女の間で生まれた子供のこと。
故人が遺言書作成時に、子どもを認知する旨を明記しておけば、認知されるだけでなく遺産相続も可能となります。
非成年後見人の指定
非成年後見人の指定は、未成年者に親権者がいない場合(死亡などの理由)、未成年者の代わりに「法律行為」や「財産管理」をする人のことを指しています。
遺言作成時に未成年の子どもがいる場合、自分が亡くなることによって親権者が不在となるケースで用いられるのが一般的です。
相続人の廃除
遺言書によって、相続人の排除を行うことも可能です。
相続人の廃除とは、遺産を渡したくない相続人から、遺産を得る権利を無くすこと。
相続人の廃除が可能となるのは、虐待や侮辱・遺産の横領といった「重大な非行」があった場合に限ります。
生命保険金受取人の変更
遺言書に、生命保険金の受取人を変更したい旨を明記することで、手続きを行わずとも受取人を変えることができます。
例えば、高齢の女性が遺言書を作成する場合。これまで、保険金の受取人を「夫」にしていたとします。
しかし、夫は自分よりも年上であり、保険金を受け取っても使い道がないと判断するケースも。
この場合、夫から子どもに受取人を変更したいと考える人も少なくありません。
本来、保険金の受取人変更は保険会社での手続きが必要となりますが、遺言書に記載しておけば手続きの必要もなく故人の意向が認められます。
遺言実行者の指定
遺言書では、遺言実行者を指定することもできます。
そもそも「遺言実行者」とは、故人の遺言に記載されている内容を実現するために、その遺言を実行する役割を担う人。
遺言書作成時に遺言実行者を指定しておくことで、自分の意向が正しく実行されます。
遺言実行者は、遺言書に書かれた内容に沿って預貯金の名義変更を行なったり、不動産の相続登記を行なったりします。
不動産の相続登記に関する詳細は、下記の記事でまとめていますので、合わせてチェックしてみてください。
遺言の効力はいつ発揮される?有効期限はあるの?
遺言の効力が及ぶ事柄については理解できましたが、実際にいつから効力が発揮されるのでしょう?
遺言書が効力を発揮するのは「作成した人が亡くなった時」です。遺言者が亡くなったときに相続が始まるため、その時点で法的効力を持ち始めます。
ただし、正しい形式で作成されていることが条件となりますので、注意しなければなりません。
また、遺言書に有効期限は定められていません。例えば、5年前、10年前に作成された遺言書であっても有効です。
遺言書が無効となるのケースとは?
遺言書の法的効力や有効期限について確認してきましたが、中には「無効」となる遺言書もあるため注意が必要です。
遺言書が無効となるのは、どのような場合なのでしょうか?無効となるケースの一例を紹介していきます。
形式に沿っていない遺言書
遺言書は、細かく定められたルールに基づいて作成しなければなりません。
例えば、自筆証書遺言であれば「遺言者が全文を自筆で作成する」という決まりがあります。日付や氏名を入れるのはもちろん、訂正する際にも細かいルールがあるため、すべてクリアしていなければならないのです。
タイトルのみパソコンで記入してしまったり、署名押印を忘れたりすると、その遺言は無効となってしまいます。
遺言当時、本人が15歳未満であった
遺言書が無効となるケース2つ目は、遺言当時、本人が15歳未満であった場合です。15歳未満の遺言者が作成したものは、無効となるため気をつけましょう。
民法では原則として、遺言書の作成は「満15歳以上」であれば、誰でも作成できます。
このことからもわかるように、未成年であってもしっかりとした意思・判断能力が備わっていれば、法的効力のある遺言書の作成をすることができるのです。
証人に適さない人が立ち会っていた場合
公正証書遺言や秘密証書遺言の作成時には「2人以上の証人の立ち会い」が義務付けられています。
しかし、証人は誰でも良いというわけではありません。下記に該当する人が証人となった場合の遺言書は、無効となってしまうため注意しましょう。
- 18歳未満の未成年者
- 推定相続人・受遺者
- 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の関係者
上記の「受遺者」とは、遺言によって財産を相続する人のことをさしています。
まとめ|遺言書は慎重に作成し法的効力を発揮させよう
本記事では、遺言書の効力が及ぶのはどのようなことなのか?有効期限や無効になってしまう遺言書の特徴について詳しく解説してきました。
遺言書にはさまざまなルールがあるため、慎重に作成しなければ無効となってしまうこともあります。
正しい遺言書を作成することができれば、数多くの内容に法的効力を持たせられることがわかりましたね。
また、遺言書には「有効期限」はありません。15歳以上の意思・判断能力が備わっている人であれば、未成年でも作成することは可能です。
今回紹介した「無効となるケース」を参考にし、法的効力のある遺言書を作成しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。